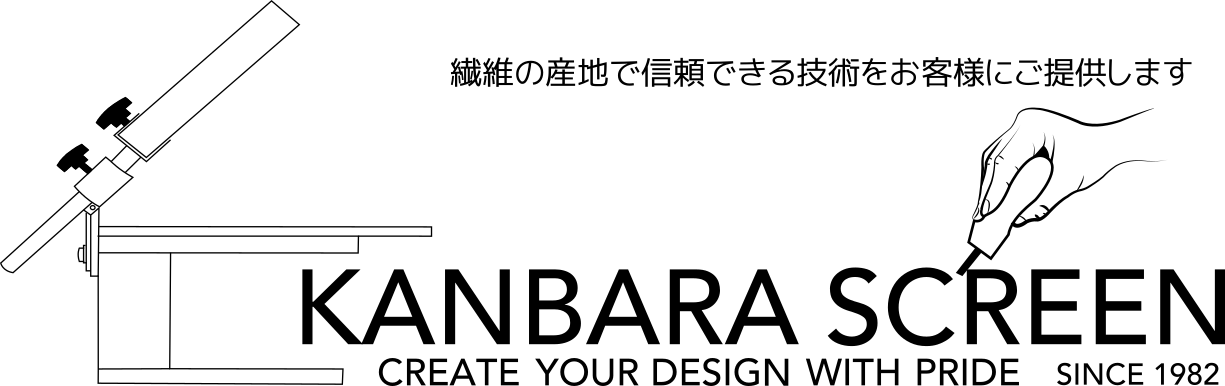いつもご覧いただき、ありがとうございます。
2月は毎年、多くのご注文をいただく 一年の中でも特に繁忙期 となっております。
そのため、通常よりも製作スケジュールが立て込みやすく、納期にお時間をいただく場合 がございます。
一つひとつの工程を大切に、品質を保ちながら進めているため、
どうしてもお時間を要してしまうことをご理解いただけますと幸いです。
ご希望の納期がある場合や、お急ぎの案件につきましては、
できるだけ早めにご相談 いただけますと、調整しやすくなります。
お待たせしてしまうこともあるかと思いますが、
その分、責任をもって丁寧に仕上げてまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。